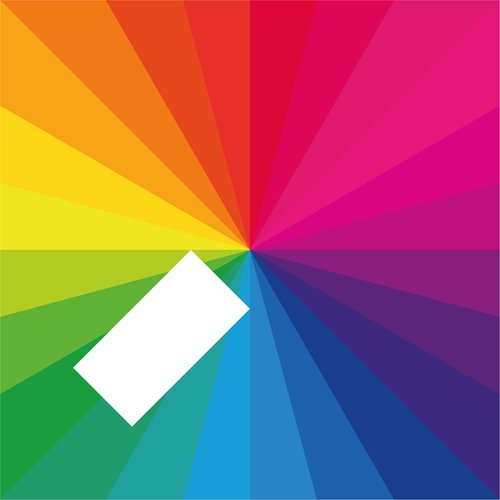【年間ベスト】2015年「 極私的」年間ベスト・アルバム _ 『2015年、圧倒的な1枚』編
本作をピカソの「ゲルニカ」に例える声がある。人間の蛮行と悪を描いた黙示録であるかの作品と同様、『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』は告発的な作品だ。それはアフリカン・アメリカンたちがホワイト・ハウスの目の前で裁判官を踏みつけ、酒ビンと札束を握りしめ歓喜の表情を浮かべるカバー・スリーブからも十二分に伝わってくるだろう。アメリカというコンセプトが建国以来内包し続ける矛盾、未だ終わることのないアフリカン・アメリカンの苦悩、そして世界中にはびこる矛盾と不条理についての告発である。
と同時に本作は一方的な告発では終わっていない。他者との対話であり、自分との対話のドキュメントだ。「Wesley's Theory」では黒人の成功者が最終的には搾取されるという構造の指摘からアルバムは始まり、「King Kunta」ではクンタ・キンテを引き合いに悪しき奴隷制度という悲劇に繰り返し言及しながらも、次第にケンドリックは一人の人間としての葛藤を露わにし始める。
人が人を変えることの難しさについて苦悩する「Institutionalized」、そして「U」では自分を愛せない苦しさを歌う。ケンドリック自身はこのアルバムを「強さ、勇気、誠意だけじゃなく、成長と承認と否定にも溢れた作品だ」と表現した。それゆえファレルを召喚した「Alright」にはAlabama Shakesのそれような歯切れはなく、重苦しさが残る。
そして、多くのブラック・ミュージックがそうしてきたように「Momma」でアフリカン・アメリカンとしてのルーツにケンドリックも目を向け、「Complexion」では黒人もまた多様であるということを指摘しながら本質主義の罠に注意を払いつつ、その多様な美を主張する。そして「i」でケンドリックはついに強い意志を持ってようやく自信を取り戻し、アイズレー・ブラザース「That Lady」のファンクネスを借りることでアルバムは最高潮を迎える。
フェラ・クティ、ジョージ・クリントン、ジェイムス・ブラウン、アイズレー・ブラザーズ、ドクター・ドレ、2PAC、スヌープといったかつてのレジェンド(=バタフライ)、つまりブラック・ミュージックの歴史そのものとケンドリックは次々と接続することで今この瞬間を前進する糧にする。過去だけではない、フライング・ロータス、ロバート・グラスパー、サンダーキャットといったLAビート/ジャズ・シーンという現在とも積極に接続していくことで、音楽的重層性(特にファンクとジャズ)だけでなく、歴史的な重層性を獲得しているのだ。そして彼らもまたキャタピラー(=イモムシ)からバタフライへと脱皮し、飛び立った者たちでもあり、各々多かれ少なかれピンプ(=搾取)を経験した者たちでもある。
日本では温度感を感じるのが難しいが、ケンドリックの新たな世代のリーダーとしての期待は、US本国では相当な熱気を帯びていると言う。ケンドリック自身も迷いを露わにしつつも、その役割を引き受けようとしているようにも見えるのが頼もしい。キング牧師やネルソン・マンデラといった過去の偉大なマイノリティ・リーダーたちを堂々と引き合いに出しながら、ケンドリックは自分たちが改めて「どこから来て、どう育ち、何に向かうのか」を問うこと、そして成功とピンプ(=搾取)の罠に警告を促すことで道を誤らないよう自らを鼓舞し、日に日に高まる影響力をポジティブに昇華しようとする。
この新たな若きリーダーは、我々が毎日世界を昨日より良い場所にしようという気持ちで朝を迎えることを決して嘲笑したりはしない。むしろ必ずや祝福してくれるに違いない。「イモムシのなかに、それがやがて蝶になることを予感させる要素はない」と語ったのはバックミンスター・フラーだが、それはつまり、どんなキャタピラーもみなバタフライになれる可能性を秘めている――「エブリ・ニガー・イズ・ア・スター」なのだから。
プリンスは「Albums still matter.(アルバムは今も重要だ)」と言ったが、この重層的に織り込まれた音楽とストーリーを持つ一大絵巻を創り上げたケンドリックは、音楽というアートフォームの可能性を、そしてアルバムというフォーマットの有効性までをも証明してしまった。2015年、圧巻の比類なき一枚。

- アーティスト: ケンドリック・ラマー,ジェイムズ・フォンテレロイ,ラプソディー,ジョージ・クリントン,ビラル,ロナルド・アイズレー,K.ダックワーズ,D.パーキンス,マシュー・サミュエルズ,T.マーティン,C.スミス
- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック
- 発売日: 2015/05/20
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
【年間ベスト】2015年「 極私的」年間ベスト・アルバム _ 『ポストEDMとしてのダンス・ミュージック』編
産業化が過ぎた快楽=EDMからの離脱
とにかく強引にフィジカルに訴えかけてこうようとするEDMには流石に世界中が食傷気味になったのか、僕が触れた2015年のダンス・ミュージックは、EDMに明確に引導を渡すような革新や派手さを持ち合わせた何かは無かった代わりに、静かに過去の遺産と接続しながら深みを与えてくれるような作品が多かったような印象があります。'10年代のダンス・ミュージックはUKが牽引してきたという言い方も過言ではないと思いますが、そんなUKを引っ張る若き中心人物と新たな才能の2作品をここでは紹介しようと思います。
・Jamie XX 『In Colour」
ジェイミー自身は足繁く世界中でDJプレイをしに飛び回ってはいるが、その内向的な性格ゆえか、アシッド・ハウスにもジャングルにも間に合っていない世代ゆえか、ここには「現場」としてのフロアの香りは全くと言っていいほど感じられない。
90年代含めた過去へのノスタルジアという想像力を目一杯含みつつも、この6、7年のキャリアの中で得た果実を全て注ぎ込むことで紡ぎ出された理想としてのダンス・ミュージックがここにはあるのだ。だが決して過剰にはならず、より少ないことでより多くのことを成している。
EDMがひたすら右肩上がりにカタルシスを上昇させようとしている中、ジェイミーはもっと様々なベクトルの感情を委ねることができるようなリズムとサウンドを提供してくれる。そして最高なのはジェイミーの音楽には「どんな最高のパーティーもいつかは終わる」ということを知っている、そんな切なさが漂っているところだ。
・Tom Misch『Beat Tape2」
こちらもジェイミーXXと同様「上半期ベスト」でも選出した作品。Floating Pointsとも迷ったが、今後のポテンシャルも踏まえた期待を込めた選出にした。トム・ミッシュは南ロンドン出身のわずか20歳のマルチ・インストゥルメンタリストにしてトラック・メーカーだ。そして彼は歌うことすら出来てしまう。それ故か彼のトラックへのアプローチは「ビートメイキング」というよりは「コンポージング(作曲)」といった方が正しそうなのはこのメイキング映像からも感じ取れる。
テクノ、ヒップホップ、ジャズと様々な要素を少しずつ横断しながらzero7的な洗練されたスムースさが彼のトラックの特徴。ただ是非、余り先入観を持たずに彼の作品を聞いて欲しい。曲毎に少しずつ様々なエレメントが織り込まれているのが聴こえてくるだろう。Floating Pointsのビートにはもはや飽和しつつあるいわゆるディラ・ビートの影響は見られないが、トム・ミッシュのそれには影響の影が絶大だ。ただ生の楽器を普段に利用している分、ただの援用には留まらないシナジーが生まれている。
トムのサウンド・メイクは基本的にはミニマルでありながら、必ずさりげなくスウィート・スポットを突いてくるのがその才能の稀有なところ。その真髄は「In the Midst of All」で最も顕著に感じ取ることが出来るはずだ。
【年間ベスト】2015年「 極私的」年間ベスト・アルバム _『絶滅が危惧される”ギター/ベース/ドラム” バンドの生き残り』編
元の居場所へと還っていく「インディー」
この10年のアメリカの音楽産業は「インディー」という鉱脈を掘り返すことで飯を食ってきたと言ってもよいだろう。ただグランジ・ブームの時の反省からか、食い尽くされ、焼き畑化される前にここ数年をかけて「インディー」は元のサイズに還っていったと僕は見ています。元来「捏造」されたマーケットではないゆえ、自分たちの居場所を適切なサイズで守ることが出来るのも米の音楽カルチャーの懐の深さだと改めて思わせてくれたのも事実です。
そして『リバイバル以後のいいとこ取りハイブリッド音楽としてのR&B』でも書いたように運営効率の悪い「バンド」という形態も相成ってか、気づいてみればメインストリームからはいわゆるギター・バンドがすっかり見当たらなくなってしまいました。
ここで紹介するのはそんな絶滅危惧である「バンド」というフォーマットで各々の形で説得力を持った作品をリリースした2組であり、共にセールス、評価双方において結果を残しました。どちらのバンドも00年代以降の「ロックをリバイバルとしてしか体験してない世代」の耳にはきっと強烈に響くはずです。
・Sleater-Kinney 『No Cities To Love』

10年ぶりに帰ってきたスリーター・キニー。きっと「Surface Envy」のギター・リフを聴いたら往年のファンは涙することを約束する。と同時にこのアルバムは最もフレッシュに、そして相変わらずシンプルだ。変わらない2本のギターのアンサブルとジャネットのドラムが鳴り響いている(このバンドはベースレスだ)。集大成でありながらも、エントリーにもベストなアルバム、そんな言い方をしてもいいかもしれない。過去作でいうと『Dig Me Out』や『All Hands On The Bad One』に近い耳障りかもしれない。
聴いているだけで感電するかと思うほど「エレキ・ギターって電気使ってるんだよな」という感じが音に出ている。ジャネット・ワイスの手数の多いドラムも程よいふくよかさと残響感を含みながら尖りまくったギター2本を支えている。リユニオンに気負った感じはなく、ど頭から最後まで走り抜ける10曲32分。
スリーター・キニーは「Price Tag」からも分かるように子供、家庭、ミドルエイジ、そういった「現実」を覚悟を持って正面から受け止めている。若ぶりも、悪ぶりも、イケてる振りもしない。その意味ではロックにおいて「ミドルエイジ」と始めて相対することに成功したザ・ナショナルと双璧を成しているのかもしれない。兎にも角にも予想の遥か上を行く嬉しい嬉しい復活作。
・Alabama Shakes 『SOUND&COLOR』
まぁとにかく音だ、音。ギターの弦とはこう鳴るもんだと言わんばかりのアタック音の凄み。「本当のギターの音」なんて分かってないんだけど、きっとこれがその音だとしたり顔で語りたくなるような芳醇な響き。そして今聴くとデビュー作は随分荒削りなもんだったなと思うほど、全体のプロダクションは洗練され、各楽器の鳴りの捉え方は研ぎ澄まされた。
ブルーズへの愛に溢れた一聴するとレトロ&シンプルなスタイルは、ある種難易度が増しすぎて取っつきにくさが目立ち始めたインディー・ロックが後景へと退いていく中、すんなりと受け入れられたのかまさかの全米一位をも獲得してしまった。が、それはアメリカ音楽史の正史を真っ当に参照点としていることだけが理由ではないだろう。2015年、それはアメリカにおいてケンドリック・ラマーが様々な「カラー」が同居することによる受難を告発した年でもあったわけだが、アラバマ・シェイクスはそれを祝福することにしたからだ。
現実を知れば知るほど、積み重なっていく歴史を考慮すればするほど、何かを短絡化して叫ぶことが空虚で危険なことだと分かってしまい、何かを言い切れなくなってしまう。そんなこんがらがった中でもアラバマ・シェイクスは「Hold On!(持ち堪えろ)」と、そして「Give me your all love!」と歌い切った。ブルーズやソウルが紡いできた常套句でもあるこれらのフレーズを2015年でしか出来ない形で、2015年のサウンドで更新したということがこの作品の価値なんじゃないだろうか?
【年間ベスト】2015年「 極私的」年間ベスト・アルバム _『リバイバル以後のいいとこ取りハイブリッド音楽としてのR&B』編
最もハイブリッドで適応性のあるフォーマットとしてのR&B
音楽のフォーマットとしてのR&Bの援用はまだまだ続いたのが2015年でした。ダンス/ベース・ミュージックとの合流を踏まえ多くの新しいR&Bが登場したイギリスだけでなく、アメリカでもいわゆるメインストリームとは異なる潮流のR&Bはメインストリームを侵食しながらポジションを築いてきたとも言えます。
僕が考えるこのR&Bというフォーマットの近年の勝因は二つ。いい加減な仮説ですが触れてみます。
ひとつは音楽制作におけるソフトウェアの進化と低価格化、およびリリース形態の民主化の急激な進歩による「バンド」という形式の「運営効率」の悪さが際立ってしまったことによるソロ・アクトの増加と、ソロと「R&B」というフォーマット相性の良さが合致したということ。
ふたつ目は、この10年の音楽的な果実(ベース・ミュージックからバロック・ポップ的意匠等々)を最もハイブリッドに吸収し、アウトプットしてきたフォーマットがR&Bだったということ。
この二つが世界的にR&Bがポップ・ミュージックの舞台からロック・バンドを追いやってきたことと関係している気がします。ただサウンドとしてのR&Bはその多様性の拡張と進化を遂げているにも関わらず、(イギリスに比べて特に)アメリカのR&Bは相変わらず「マッチョな男らしさ」と「ナルシスティックな官能」だけをダラダラと歌っておいて、更新感がないのも事実です。
以上のことを踏まえ、ここではサウンドとしてのR&Bの折衷性を象徴する1枚とR&Bが「何を歌うか」を米メインストリームから更新した1枚を紹介します。
・Miguel 『Wildheart」
ミゲルはR&Bが未だ変わらず引きずっている「マッチョな男らしさ」へ抗ってみせている。メインストリームのR&Bの舞台ではジェレマイアやらトレイ・ソングズたちがウンザリするほどひたすらセックスと愛、ほとばしる汗について歌っている。このミゲルもテーマは同じだが、アングルが違う。前者がひたすら男が快楽に浸ることだけを歌っているとしたら、ミゲルのそれはパートナーとの交歓についてフォーカスしている。これは”インディーR&B/ オルタナティヴR&B”においてザ・ウィークエンドがひたすら病んだナルシシズムを撒き散らしているのとも決定的に違う。
加えてそのサウンド。リリックの官能性を彩るように全体にシルキーとでもいうべき音像に仕上がっているが、そのケバケバしいほどのサイケデリア、ファンク的なノリ、懐古的でありながら同時にモダンなサウンドがあらゆるジャンルを飲み込んでいくその様はファレル・ウィリアムスが率いた最盛期のN.E.R.Dと重なる部分があるし、それらの更新性こそがミゲルがプリンスとよく比較され「ネオR&B」なる呼称が与えられる由縁なのかもしれない。セルフ・プロデュースの裏方としては、ジェシー・ウエアやマルーン5、リン・ウィーバーでも有名なベニー・ブランコやカシミア・キャットがミゲルのあらゆるジャンルを横断していくサポーターを的確に努めている。
ライブ・パフォーマンスを観ると公言している通りフレディ・マーキュリーやジェームス・ブラウンといったレジェンドたちの影響も垣間見えるが、過去の偉人の力を借りながらミゲルはソウル/R&Bを前に押し進めようとしているのかもしれない。そこにおいては性や官能はマッチョな「男らしさ」ではなく「パートナーとの交歓される想い・喜び」を祝福するものなのだとでも言うように。
(#それにしてもこのジャケット、なんとかならなかったのだろうか・・・笑)
・Unknown Mortal Orchestra『Multi Love」
2015年はベッドルーム・サイケデリアから這い出てきたアクトが目立った年でもあった。ご存知のテーム・インパラ、トロ・イ・モア、そしてアンノウン・モータル・オーケストラ(以下、UMO)。テーム・インパラの評価は正直インフレし過ぎていると思うが、その「いいとこ取り」感とR&Bへの接近による「分かりやすさ」が鍵だったのかもしれない。ただテームに比べて評価の声が少ない後者2組こそ自分たちの音楽を作ったし、質的にも軍配が上がるというのが僕の印象だ。
本作『Multi Love』は中心人物ルーベン・ウィルソンのルーツでもある60年代のサイケの気配を残しながらも彼自身が影響を強く受けているR&Bへの接近だけでなく、ファンクそしてディスコを横断しており非常に折衷的だ。そして最終的にはコンパクトに、そしてキャッチーにまとめることに成功している。特に超絶キャッチーなベース・ラインを持つ「Can’t Keep Checking My Phone」は1年の中でも屈指の名曲と言っていい。
根っからの機材オタクでもあるルーベンが多くのアナログ機材を駆使して作った音像は、音遊びにはストイックであっても音楽シーンのトレンドに目配せしている様子はあまり感じられない。ルーベンはミュージシャン一家でもあり、レコーディングには父や弟も参加しているリラックスしたムードも漂う作品ながら、テームの存在もありそのサウンドが図らずも時代のタイミングにハマッたということかもしれない。時の風化により耐えうるのはテームよりこのUMO、そんな予感を与えた良作だった。
【年間ベスト】2015年「 極私的」年間ベスト・アルバム _ 『埋もれた日常を掘り起こす想像力としてのフォーク・ミュージック』編
埋もれた日常を掘り起こす想像力
ここで紹介する二組は「グローバル・ポップ」で紹介した面々や、アデルのような最先端のプロダクションの凄みはありません。そしてラブ・ソング、とりわけ失恋という形式というユニバーサル・ランゲージを分かりやすく採用してくれているわけでもありません。
彼らの紹介する音楽は、極めてパーソナルな日常、そして感情の振れ幅が大きいモチーフではなく、いつだって見過ごされ、フォーカスされることなんてなさそうな些細な事象や感情に目を向け、掬い取ってみることで新たな景色を浮かび上がらせる音楽です。それは正にフォーク・ミュージックの本質でもあり、脈々と受け継がれてきたものでもあります。
また音響面においても「アコギをポロリと爪弾くだけ」というフォークという単語で連想するステレオタイプなイメージからは実は程遠いということも忘れないでください。00年代以降の様々な音楽的な実りを取り込みながら、音響的なレイヤーのバラエティを増やしてきた現在のフォーク・ミュージックとはいかなるものか?という視点でも聴いてみることも是非オススメします。
・Sufjan Stevens 『Carrie & Lowell」

フォーク・ミュージック。それはポロポロとアコギを奏でながら素朴なメロディを歌う・・・。そんなステレオタイプなシンガー・ソングライター像を更新したことはスフィアンのアーティストとしての大きな功績の一つだ。圧倒的な音響的な豊かさ ーーアコースティックな響きを中心に据えつつも、エレクトロニクスやリズムにおける繊細な工夫は集大成的でもあるーー はどう考えても00年代以降でしか有り得ないものだ。
そして彼のもう一つの功績とは、「想像力の重要性」を改めて提示している点だ。外的であれ、内的であれ個人にもたらされた衝撃への処方箋/衝撃緩衝材としての想像力の重要性。スフィアンは継父という絶対的な他者である存在や疎遠だった実母との不安定な生活をモチーフに、現実から一旦距離を置きつつも、想像の中で改めて対象を理解し寄り添おうと努めている。そして不安定な家族という極めてパーソナルなモチーフを扱いながらも「他者との折り合い・共生」を巡る異民族が入り混じることで出来上がった国=アメリカの葛藤、矛盾や罪を図らずも照射してしまうのは彼のアーティストとしての業なのだろうか。
音楽という些細な想像力という杖が人をどこまで支えられるのか?という問いに確信を持てないながらも、まだかすかに希望が感じられる。そんな作品だ。
・Andy Shauf 『The Bearer of Bad News」
上半期ベストでも2位に選んだAndy Shauf。2008年にデビュー作をリリースした後、カナダにある両親の自宅ガレージで4年を掛けじっくり温めてきた本作品はギター、クラリネットやストリングスといった楽器の音色を繊細に扱いまとめ上げる技術において既に洗練の域に達していることを明確に示している。
そしてこのAndy Shaufもまたスフィアンと同様、誰もが見過ごす日常の些細な何気ない瞬間、感情のひだに気付き、すくい上げることが出来る作家だ。
眠ることができずにひたすら思考が逡巡する夜(「I’m Not Falling Asleep」)や、人の強欲さ(「You’re Out Wasting」)、友人の妻との不倫(「Wendell Walker」)といった日常に潜むダークサイド、感情のパンドラの箱を様々な登場人物の視点から解き放ちつつ物語を語っていく。その有様まるで「音楽では到達できないところに音楽で火を灯す」、そんな試みに映る。新たなストーリー・テラーの登場である。